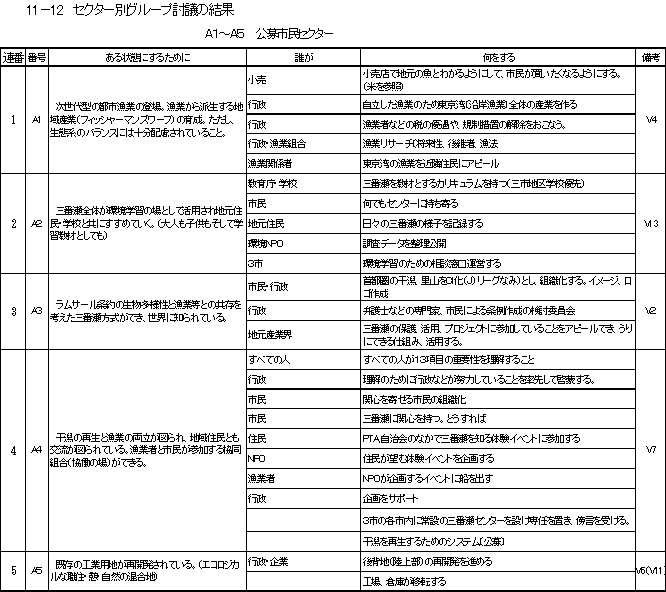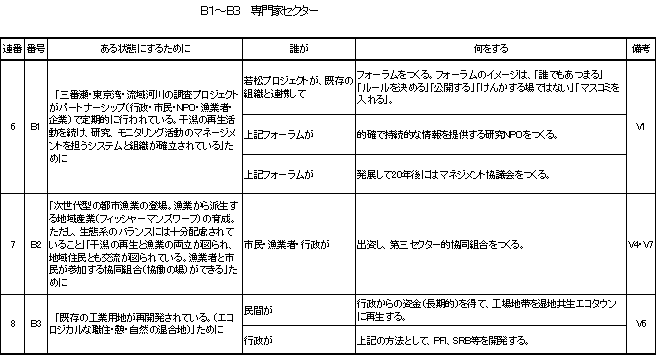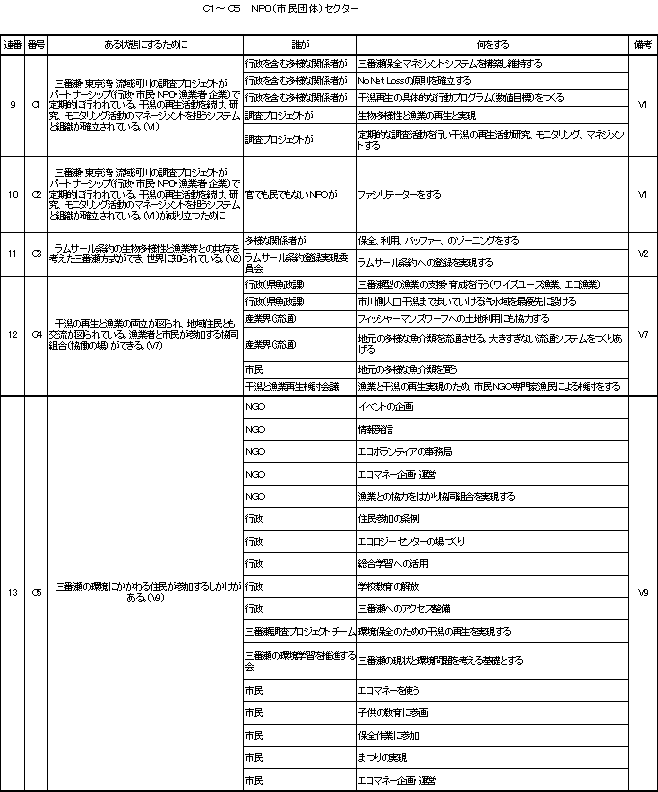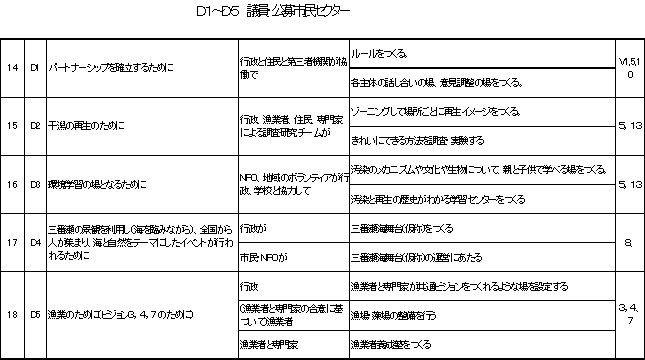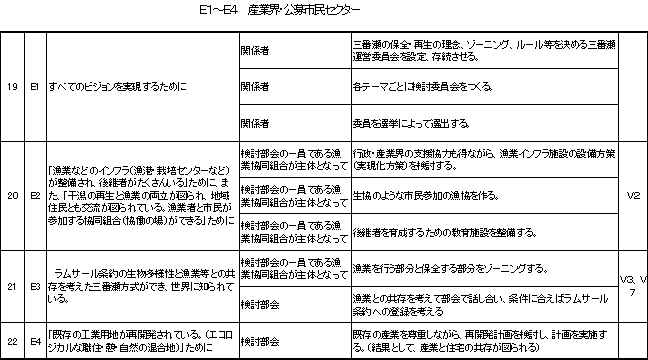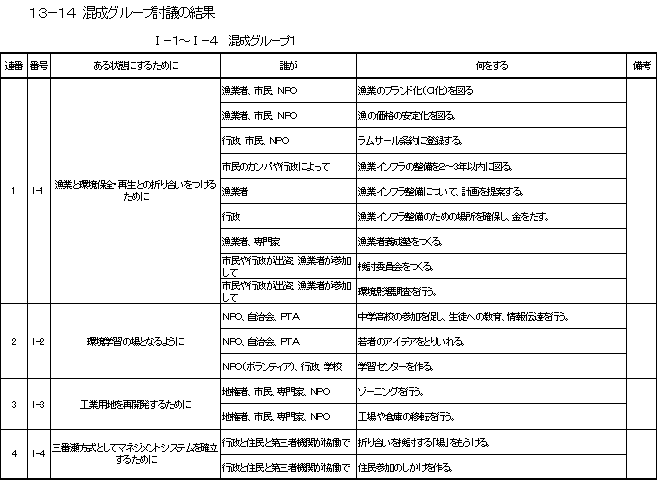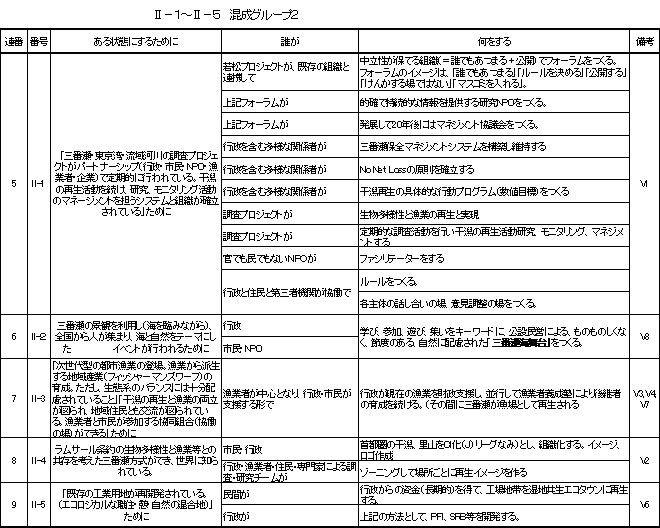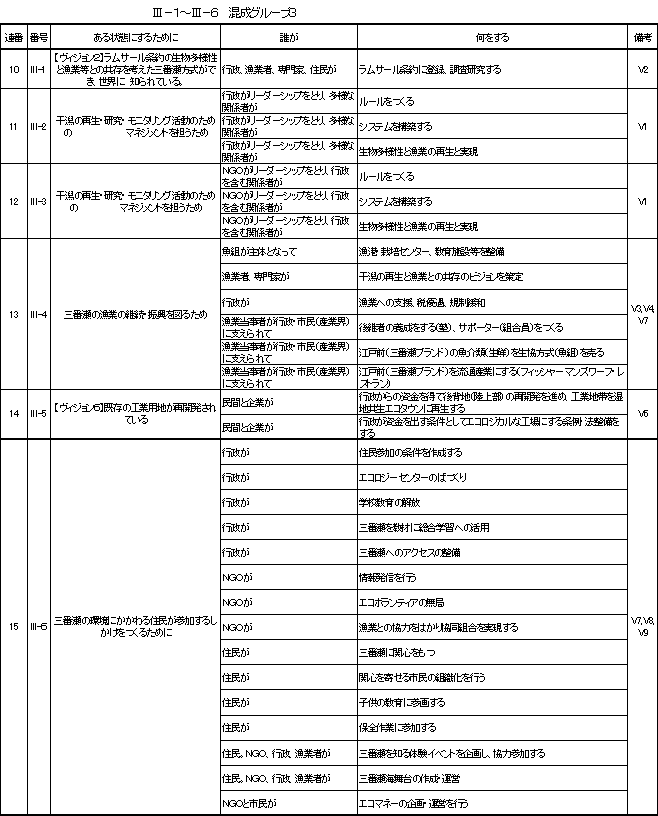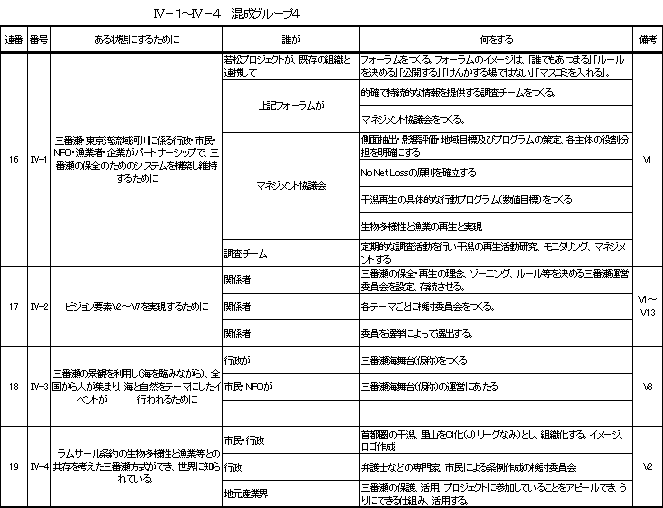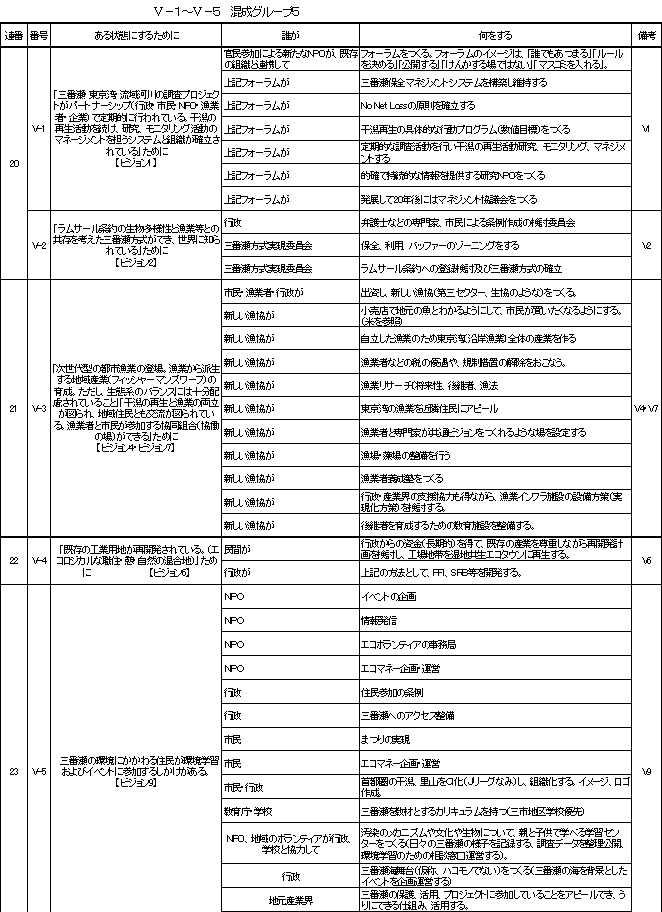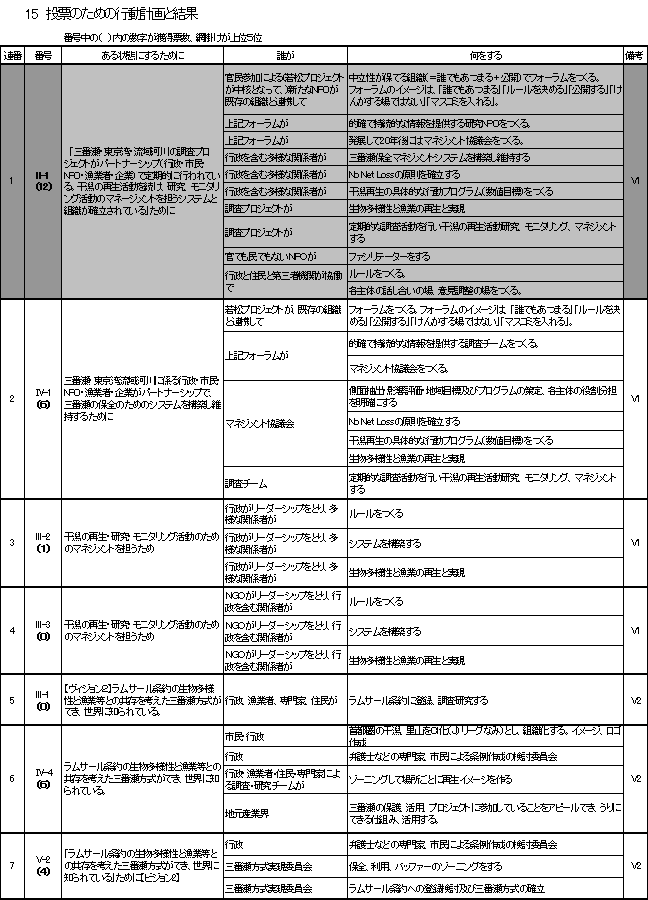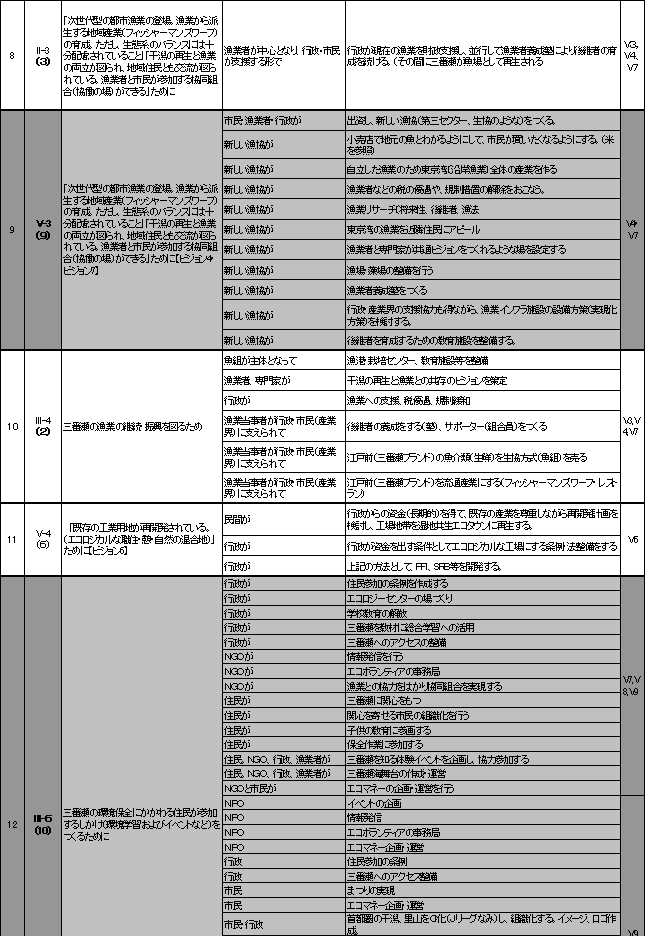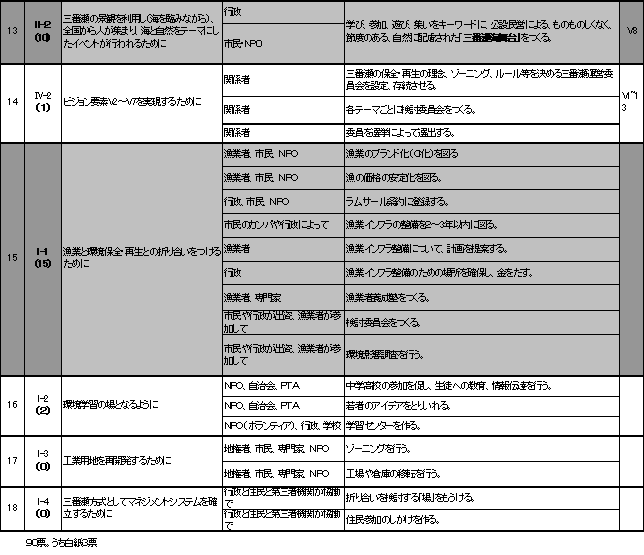���ڎ�
�v��
�P�D�J����
�Q�D���[�N�V���b�v�̐i�ߕ��Ɠ��e
�R�D�̑����ꂽ�s���v��
�P�@�V�i���I�E���[�N�V���b�v��R���̉^�c�ɂ���
�Q�@�O���[�v�\���\
�R�@��R��Z�N�^�[�ʃO���[�v���c�i�s���v��v�f��P���āj
3.1�@����s���Z�N�^�[
3.2�@���ƃZ�N�^�[
3.3�@NPO�i�s���c�́j�Z�N�^�[
3.4�@�c���E����s���Z�N�^�[
3.5�@�Y�ƊE�E����s���Z�N�^�[
�S�@��R���O���[�v���c�i�s���v��v�f��Q���āj
4.1�@�����O���[�v2-1
4.2�@�����O���[�v2-2
4.3�@�����O���[�v2-3
4.4�@�����O���[�v2-4
4.5�@�����O���[�v2-5
�T�@���[�̂��߂̍s���v��ƌ���
�v��
�P�D�J������
�J�����F2003�N5��31���i�y�j�@10:00�`17:35
�J�Ïꏊ�F��t�H�Ƒ�w�Óc���Z�ɂV���قS�K�i7404�E7405�����j
�Q���ҁ@�F�ߑO29�l���ߌ�30�l
���Ƀt�@�V���e�[�^�[�A�^�c�ψ��A�����ǁA�����ǃ{�����e�B�A
�Q�D���[�N�V���b�v�̐i�ߕ��Ɠ��e �i�P�j���[�N�V���b�v�̐i�ߕ�
�@�����z�z���������u�V�i���I�E���[�N�V���b�v��R���̉^�c�ɂ��āv�ɏ]���Đi�s�����B���̃��[�N�V���b�v�̉^�c�́A�u�w�O�Ԑ��̖������l����V�i���I�E���[�N�V���b�v�x�ɎQ���������̃}�j���A���v�Ɋ�Â��Ă��邪�A�Ō�̐헪�I���[�ɂ����鎞�Ԃ𑽂����邽�߂ɁA�X�P�W���[���S�̂������O�|���ɂ����B�܂��A�v��v�f�̏������A�v��v�f������Ƃ��̍l�����A�v��v�f�̐������m�ɂ����B
�i�Q�j���[�N�V���b�v�̓��e
�T���R�P��
| �P�@�@��V��S�̉�
�i10:05�`10:30�j |
�����̉ۑ�A�X�P�W���[���A���[���ɂ��Đ��������B
���u�V�i���I�E���[�N�V���b�v��R���ڂ̉^�c�ɂ��āv
���u�O���[�v�\���\�v |
| �Q�@�@��R��Z�N�^�[�ʃO���[�v���c
�i10:30�`11:50�j |
�e�Z�N�^�[�ʂ̃O���[�v���A���ꂼ��T�ȓ��̍s���v��v�f���쐬�����B |
| �R�@�@��W��S�̉�
�i12:50�`13:30�j |
�e�O���[�v���炻�ꂼ��̍s���v��v�f�Ăɂ��Ă̕��������B���v22������o���ꂽ�B
���u�Z�N�^�[�ʃO���[�v���c�̌��ʁv |
| �S�@�@��R���O���[�v���c
�i13:30�`15:10�j |
�V���������O���[�v���A22���̍s���v��v�f����A�C�ӂɂT���x��I�����āA������������B����23�����c�_���ꂽ�B
���u�O���[�v�\���\�v |
| �T�@�@��X��S�̉�
�@�i15:10�`15:35�j
�A�i16:00�`17:10�j |
�@
�e�O���[�v�����ꂼ��̍s���v��p�f�āi�v23���j�ɂ��ĕ����B
���u�����O���[�v�ʓ��c�̌��ʁv
�A
�d������s���v��v�f�����������B���̌���18���ɍi��ꂽ�B
���u���[�̂��߂̍s���v��ƌ��ʁv |
| �U�@�헪�I���[�E�J�[�E���\
�i17:13�`17:35�j |
�����������ꂽ18�̍s���v��v�f�ɑ��āA��l3�[�i�v90�[�j�̓��[�������Ȃ��A���5�ʂ܂ł��s���v��Ƃ��č̑����ꂽ�B
���u���[�̂��߂̍s���v��ƌ��ʁv |
�R�D�̑����ꂽ�s���v��
���̂T�̍s���v�悪�̑����ꂽ�B
�P�D ���ƂƊ��ۑS�E�Đ��Ƃ̐܂荇�������邽�߂Ɂ@�@�@�i�P�T�[�j
�E ���ƎҁA�s���A�m�o�n���A���Ƃ̃u�����h���i�b�h���j��}��
�E ���ƎҁA�s���A�m�o�n���A���̉��i�̈��艻��}��B
�E �s���A�s���A�m�o�n���A�����T�[�����ɓo�^����B
�E �s���̃J���p��s���ɂ���āA���ƃC���t���̐������Q�`3�N�ȓ��ɐ}��B
�E ���Ǝ҂��A���ƃC���t�������ɂ��āA�v����Ă���B
�E �s�����A���ƃC���t�������̂��߂̏ꏊ���m�ۂ��A���������B
�E ���ƎҁA���Ƃ��A���Ǝҗ{���m������B
�E �s����s�����o���A���Ǝ҂��Q�����āA�����ψ��������B
�E �s����s�����o���A���Ǝ҂��Q�����āA���e���������s���B
�Q�D �u�O�Ԑ��E�����p�E����͐�̒����v���W�F�N�g���p�[�g�i�[�V�b�v�i�s���E�s���ENPO�E���ƎҁE��Ɓj�Œ���I�ɍs���Ă���B�����̍Đ������𑱂��A�����A���j�^�����O�����̃}�l�[�W�����g��S���V�X�e���Ƒg�D���m������Ă���v���߂Ɂ@�@�@�i�P�Q�[�j
�E �����Q���ɂ��(�ᏼ�v���W�F�N�g�����j�ƂȂ��āA)�V����NPO�������̑g�D�ƘA�g���āA���������ۂĂ�g�D�i���N�ł����܂�{���J�j�Ńt�H�[����������B�t�H�[�����̃C���[�W�́A�u�N�ł����܂�v�u���[�������߂�v�u���J����v�u�������ł͂Ȃ��v�u�}�X�R�~������v�B
�E ��L�t�H�[�������A�I�m�Ŏ����I�ȏ�����錤��NPO������B
�E ��L�t�H�[�������A���W����20�N��ɂ̓}�l�W�����g���c�������B
�E �s�����܂ޑ��l�ȊW�҂��A�O�Ԑ��ۑS�}�l�W�����g�V�X�e�����\�z���ێ�����B
�E �s�����܂ޑ��l�ȊW�҂��ANo Net Loss�̌������m������B
�E �s�����܂ޑ��l�ȊW�҂��A�����Đ��̋�̓I�ȍs���v���O�����i���l�ڕW�j������B
�E �����v���W�F�N�g���A�������l���Ƌ��Ƃ̍Đ��Ǝ����B
�E �����v���W�F�N�g���A����I�Ȓ����������s�������̍Đ����������A���j�^�����O�A�}�l�W�����g����B
�E ���ł����ł��Ȃ��m�o�n���A�t�@�V���e�[�^�[������B
�E �s���ƏZ���Ƒ�O�ҋ@�ւ������ŁA���[��������B
�E �s���ƏZ���Ƒ�O�ҋ@�ւ������ŁA�e��̘̂b�������̏�A�ӌ������̏������B
�R�D
�O�Ԑ��̊��ۑS�ɂ������Z�����Q�����邵�����i���w�K����уC�x���g�Ȃǁj�����邽�߂Ɂ@�@�@�i�P�O�[�j
�E �s�����A�Z���Q���̏����쐬����B
�E �s�����A�G�R���W�[�Z���^�[�̏�Â���B
�E �s�����A�w�Z����̉���B
�E �s�����A�O�Ԑ������ނɑ����w�K�ւ̊��p�B
�E �s�����A�O�Ԑ��ւ̃A�N�Z�X�̐����B
�E �m�f�n���A��M���s���B
�E �m�f�n���A�G�R�{�����e�B�A�̎����ǁB
�E �m�f�n���A���ƂƂ̋��͂��͂��苦���g������������B
�E �Z�����A�O�Ԑ��ɊS�����B
�E �Z�����A�S����s���̑g�D�����s���B
�E �Z�����A�q���̋���ɎQ�悷��B
�E �Z�����A�ۑS��ƂɎQ������B
�E �Z���E�m�f�n�E�s���E���Ǝ҂��A�O�Ԑ���m��̌��C�x���g����悵�A���͎Q������B
�E �Z���E�m�f�n�E�s���E���Ǝ҂��A�O�Ԑ��C����̍쐬�E�^�c�B
�E �m�f�n�Ǝs�����A�G�R�}�l�[�̊��E�^�c���s���B
�E �m�o�n���A�C�x���g�̊��B
�E �m�o�n���A��M�B
�E �m�o�n���A�G�R�{�����e�B�A�̎����ǁB
�E �m�o�n���A�G�R�}�l�[���E�^�c�B
�E �s�����A�Z���Q���̏��B
�E �s�����A�O�Ԑ��ւ̃A�N�Z�X�����B
�E �s�����A�܂�̎����B
�E �s�����A�G�R�}�l�[���E�^�c�B
�E �s���E�s�����A��s���̊����A���R���b�h���iJ���[�O�Ȃ݁j���A�g�D������B�C���[�W�A���S�쐬�B
�E ���璡�E�w�Z���A�O�Ԑ������ނƂ���J���L�����������i�O�s�n��w�Z�D��j�B
�E NPO�A�n��̃{�����e�B�A���s���A�w�Z�Ƌ��͂��āA�����̃��J�j�Y���╶������ɂ��āA�e�Ǝq���Ŋw�ׂ�w�K�Z���^�[������i���X�̎O�Ԑ��̗l�q���L�^����A�����f�[�^�����J�A���w�K�̂��߂̑��k�����^�c����j�B
�E �s�����A�O�Ԑ��C����i���́A�n�R���m�łȂ��j������i�O�Ԑ��̊C��w�i�Ƃ����C�x���g�����^�c����j�B
�E �n���Y�ƊE���A�O�Ԑ��C����i���́A�n�R���m�łȂ��j������i�O�Ԑ��̊C��w�i�Ƃ����C�x���g�����^�c����j�B
�E �s���E���ƎҁE�s�����A�������ɊC�̂��ݏE���A���̏������J�n����i���̃N���[���A�b�v�ƂƂ��ɊC�̃N���[���A�b�v�j�B
�E ���Ǝ҂Ɛ��Ƃ��A���Ǝҗ{���m������B
�S�D
�O�Ԑ��̌i�ς𗘗p���i�C��Ղ݂Ȃ���j�A�S������l���W�܂�A�C�Ǝ��R���e�[�}�ɂ����C�x���g���s���邽�߂Ɂ@�@�@�i�P�O�[�j
�E �s���E�s���ENPO���A�w�сA�Q���A�V�сA�W�����L�[���[�h�ɁA���ݖ��c�ɂ��A���̂��̂����Ȃ��A�ߓx�̂���A���R�ɔz�����ꂽ�u�O�Ԑ��C����v������B
�T�D �u������^�̓s�s���Ƃ̓o��B���Ƃ���h������n��Y�Ɓi�t�B�b�V���[�}���Y���[�t�j�̈琬�B�������A���Ԍn�̃o�����X�ɂ͏\���z������Ă��邱�Ɓv�u�����̍Đ��Ƌ��Ƃ̗������}���A�n��Z���Ƃ��𗬂��}���Ă���B���Ǝ҂Ǝs�����Q�����鋦���g���i�����̏�j���ł���v���߂Ɂ@�@�i�X�[�j
�E �s���E���ƎҁE�s�����A�o�����A�V���������i��O�Z�N�^�[�A�����̂悤�ȁj������B
�E �V�����������A�����X�Œn���̋��Ƃ킩��悤�ɂ��āA�s�������������Ȃ�悤�ɂ���B�i�Ă��Q�Ɓj�B
�E �V�����������A�����������Ƃ̂��ߓ����p�k�����Ɓl�S�̂̎Y�Ƃ����B
�E �V�����������A���Ǝ҂Ȃǂ̐ł̗D����A�K���[�u�̉����������Ȃ��B
�E �V�����������A���ƃ��T�[�`�i�������A��p�ҁA���@�j�B
�E �V�����������A�����p�̋��Ƃ��ߗZ���ɃA�s�[���B
�E �V�����������A���Ǝ҂Ɛ��Ƃ����ʃr�W�����������悤�ȏ��ݒ肷��B
�E �V�����������A����E����̐������s���B
�E �V�����������A���Ǝҗ{���m������B
�E �V�����������A�s���E�Y�ƊE�̎x�����͂����Ȃ���A���ƃC���t���{�݂̐ݔ�����i����������j����������B
�E �V�����������A��p�҂��琬���邽�߂̋���{�݂�����B
�ȏ�S�T�U�[�^�X�O�[
�P�@�V�i���I�E���[�N�V���b�v��3���̉^�c�ɂ���
2003�N5��31��
�V�i���I�E���[�N�V���b�v�^�c������
�{���͈ȉ��̂悤�ɉ^�c���܂��i�X�P�W���[���͂����ނ˃}�j���A���ɏ]���܂����A�Ō�̐헪�I���[�ɂ����鎞�Ԃ𑽂����邽�߂ɁA�����O�|���ɂ��܂����j�B
10�F00�`10�F30�@�S�̉�7���
�@�����肵�Ă���w�L�^�b��Łx�i������������r�W�������|�[�g�Ƃ��܂��j���g���āA�T��17���A18���̐��ʂ�U��Ԃ�܂��B�����āA����ꂽ13���ڂ��琬��r�W�����i�ʂɂ��ꂾ��������������̂����z�肵�܂��j���m�F���܂��B
�@ �{���̐i�ߕ��A�X�P�W���[���A�ۑ�ɂ��Đ������܂��B
�@ �{���̉ۑ�́A����ꂽ20�N��̖��������������邽�߂̍s���v��̍쐬�ł��B��̃O���[�v���_���o�āA�s���v��v�f���쐬���A�{���̗[���ɍs���v��v�f�𓊕[�ɂ����čs���v������肵�܂��B
10�F30�`11�F50�@�Z�N�^�[�ʃO���[�v3���
�@�c�_�̉ۑ�͍s���v��v�f�̍쐬�ł��B�������i13���ڂ��琬��j���������邽�߂ɁA�e�Z�N�^�[�͉������ׂ����ɂ��āA�c�_�̂����e�O���[�v�͂T�ȓ��̍s���v��v�f��P���Ă��쐬���܂��B�u�e�Z�N�^�[�v�Ƃ́A����̃Z�N�^�[�ł���ꍇ�ƁA���Z�N�^�[�ɑ��钍���ł���ꍇ���܂܂�܂��B
���v��v�f�̏������F
�u����r�W�����v�f���������邽�߂Ɂv�A�u�N���v�A�u��������v�B
�܂��́A
�u����r�W�����v�f������������������藧���߂Ɂv�A�u�N���v�A�u��������v�B
�̂ǂ��炩�Ƃ��܂��B
�u�N���v�́A�ЂƂ̎�̂�Z�N�^�[�ł��A�����̎�̂�Z�N�^�[�̋����ł����\�ł��B
���u����r�W�����v�f������������������藧���߂Ɂv�Ƃ������R�F
�@ �r�W�����v�f�ɂ́A���ڂɂ����ڕW�Ƃ��Čv��𗧂Ă�����̂�����ł��傤�B�������A����r�W�����v�f���������Ă��邽�߂ɂ́A�������̏������������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ��l�����܂��B�����ŁA���̏����i�����̏ꍇ������ł��傤�j���������邽�߂ɍ\�z�����v��v�f���o�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����z�肵�Ă��邽�߂ɁA���̕\����p���Ă��܂��B
���s���v��v�f������Ƃ��̍l�����F
�P�D������ł͂Ȃ����̂�����Ă��������B
�Q�D����͍s������̎Q���҂����Ȃ��̂ŁA�u�悢�v��ł���A�s���͂�����̗p���ĉ������Ă����v�ƍl���邱�Ƃɂ��܂��B
���s���v��v�f�̐�����
�@�ЂƂ́u�r�W�����v�f���������邽�߂Ɂv�A�������u�N���v�u��������v���o�Ă����Ƃ��ɂ́A�ʁX�ɐ�����̂ł͂Ȃ��A�u�r�W�����v�f�v���ɂ܂Ƃ߂ĂP�Ɛ����܂��B�u�r�W�����v�f������������������藧���߂Ɂv�̂Ƃ��������ł��B
�@�������A�������ɖ�������u��������v���܂܂�Ă���Ƃ��ɂ́A�ʂ̂��̂Ƃ��Đ����܂��B
11�F50�`12�F50�@���H�E�x�e
12�F50�`13�F20�@�S�̉�8���
�@�e�O���[�v�͍s���v��v�f��P���Ă\���܂��B
13�F20�`14�F40�@�����O���[�v3���
�@�����ŁA���̍����O���[�v�̐V���ȍ\�������m�点���܂��B
�@�e�O���[�v�͂���܂łɓ���ꂽ25���ȓ��̍s���v��v�f��P���Ă���A�T�ȓ��i�������A���ӂ�����ȏꍇ�A�e�O���[�v�̃����o�[�̐��܂ŋ��e���܂��j�i����́A�}�j���A���Ɏ��������[������̕ύX�ł��j��I�����A����������ĂT�ȓ��̍s���v��v�f��Q���Ă��쐬���܂��B
14�F40�`15�F00�@�x�e
15�F00�`17�F10�S�̉�9���
15�F00�`15�F30
�@ �e�O���[�v�͍s���v��v�f��Q���Ă\���܂��B
15�F30�`16�F10
�@
�d������s���v��v�f���Q���҂̋c�_�ɂ���Đ����������܂��B�������A�������ӂ͐}��Ȃ����ƂƂ��܂��B
16�F10�`16�F30�@�x�e
16�F30�`17�F10�@�헪�I���[�E�J�[�E���\
�@ �Q���҂͈�l��3�[�������A�����������ꂽ�s���v��v�f��Q���Ăɑ��āA�헪�I���[�����܂��B���[�I����A���J�ŊJ�[���܂��B
�@ ���[���ʂ\���A��ʂT�����̃��[�N�V���b�v�̍s���v��Ƃ��܂��B
���@�X�P�W���[���I����A�L�Ҕ��\���܂��B
�Q�@�O���[�v�\���\
�O���[�v�\���\�i31���j |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| �t�@�V���e�[�^�[ |
���� |
���� |
���� |
���� |
���� |
| ���L |
�O�� |
���� |
�v�� |
�c�� |
�� |
| �⏕ |
�㓡 |
���[ |
���� |
���� |
��� |
| �Z�N�^�[�� |
���� |
�ӌ��c�� |
�c�� |
�Y�ƊE |
����s�� |
| �Ȗ����Y |
�ĒJ���� |
����p�� |
�X�{�� |
���o�C |
| �����_�i |
�R�^�� |
���Ƃ������� |
�g������ |
�Ē��� |
| �ˑ��M�v |
��z���� |
�������q |
�x�ؐM�s |
���{���u |
| �{���S�� |
�쓇��ߎq |
����M |
����h�� |
���։��� |
| �c���G�� |
���Ԉ�W |
���V�M���Y |
���ΗT�� |
���ԓN�Y |
| ���{�ޕ�q |
���g�@�� |
��؍O�V |
|
�͓c���� |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
�͌���s�� |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| �t�@�V���e�[�^�[ |
���� |
���� |
���� |
���� |
���� |
| ���L |
�c�� |
�� |
���� |
�v�� |
�O�� |
| �⏕ |
���� |
��� |
�ז� |
���� |
�㓡 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| �����O���[�v�Q |
�ˑ��M�v |
�c���G�� |
���{�ޕ�q |
�Ȗ����Y |
�����_�i |
| �{���S�� |
�R�^�� |
��z���� |
�ĒJ���� |
�쓇��ߎq |
| ���Ԉ�W |
���g�@�� |
�X�{�� |
�g������ |
�x�ؐM�s |
| �������� |
����M |
����h�� |
���։��� |
���ԓN�Y |
| ���{���u |
�͓c���� |
����p�� |
���ΗT�� |
�Ē��� |
| ���Ƃ������� |
�������q |
���o�C |
���V�M���Y |
��؍O�V |
�R�@��R��Z�N�^�[�ʃO���[�v���c�i�s���v��v�f��P���āj
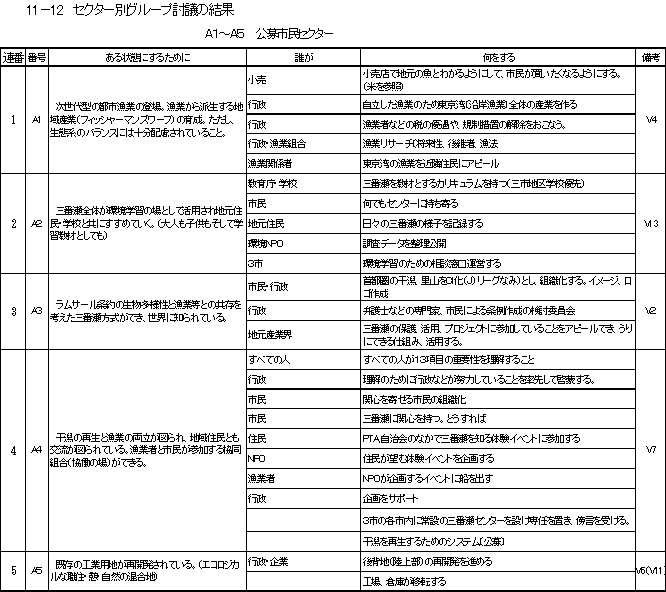
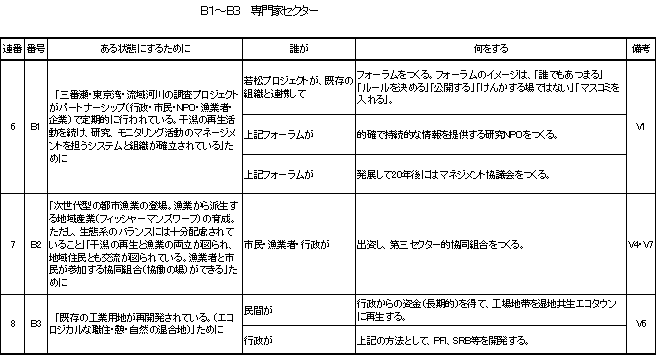
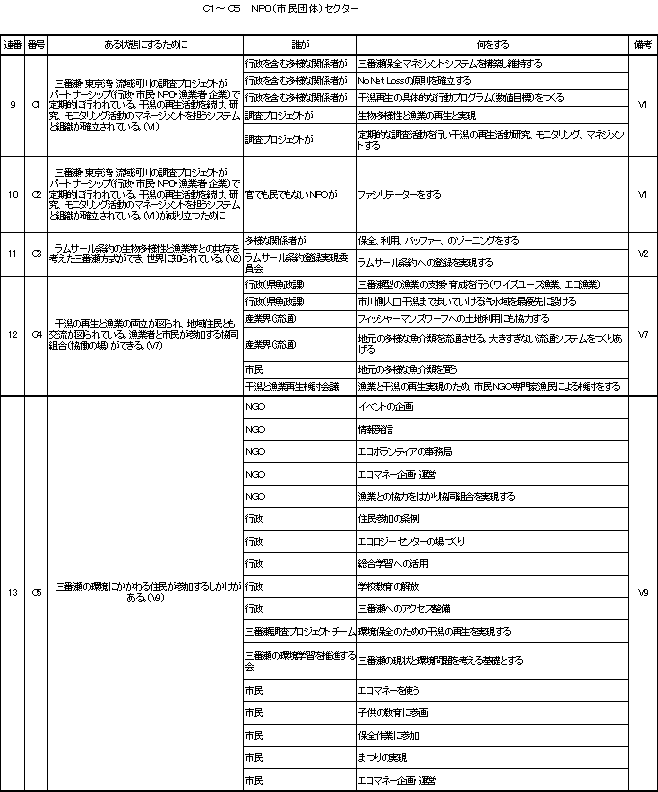 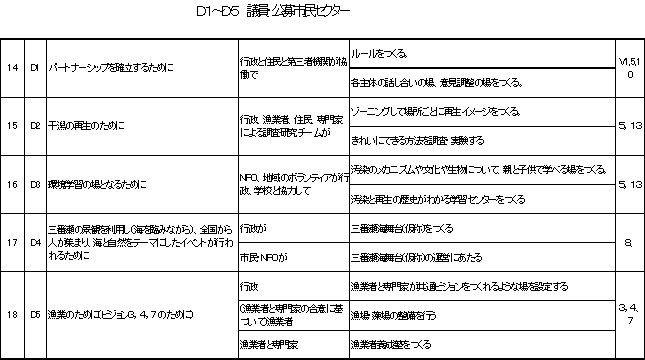
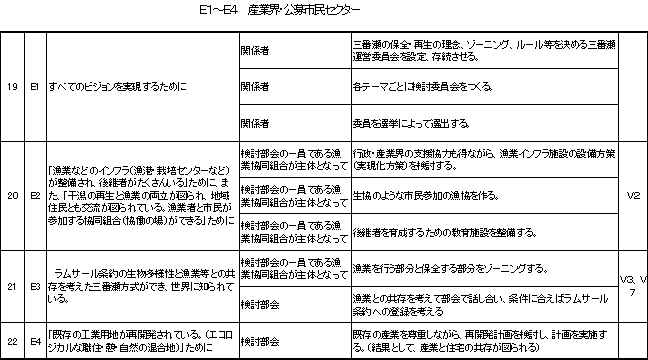
�S�@��R���O���[�v���c�i�s���v��v�f��Q���āj
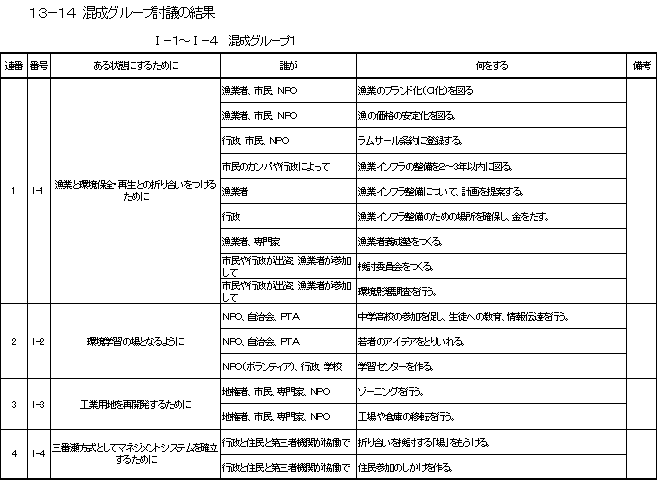
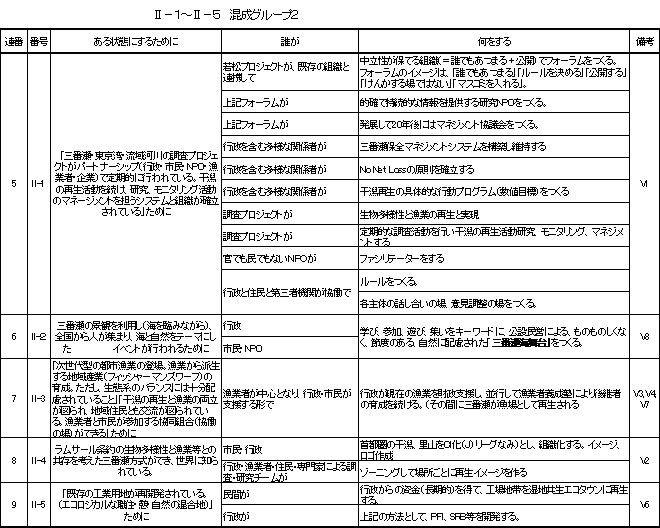
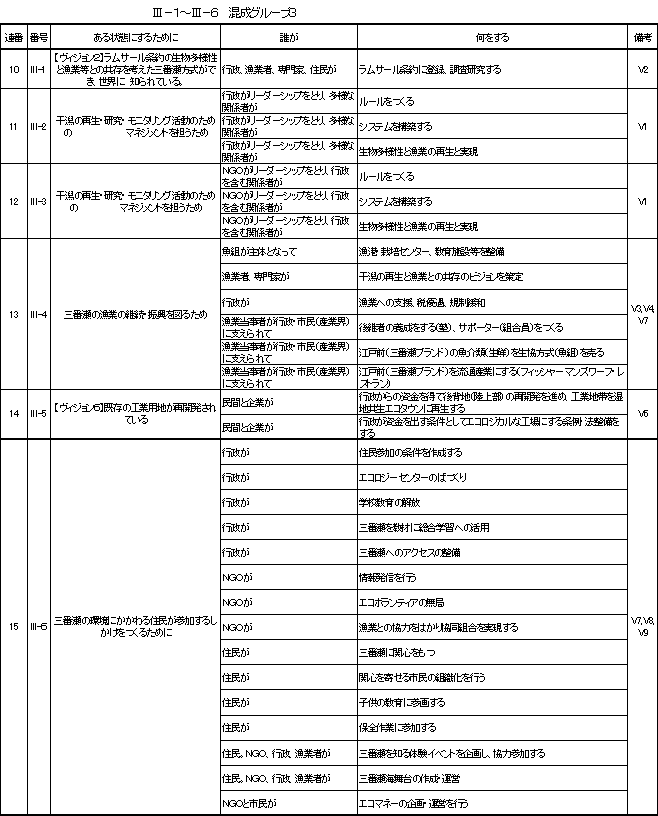
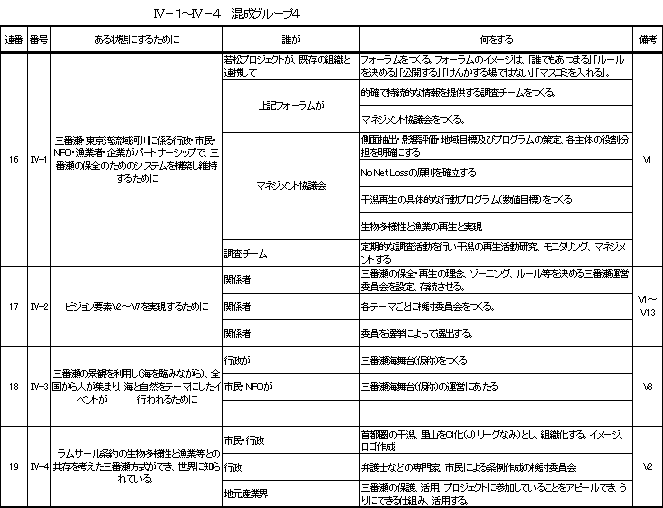
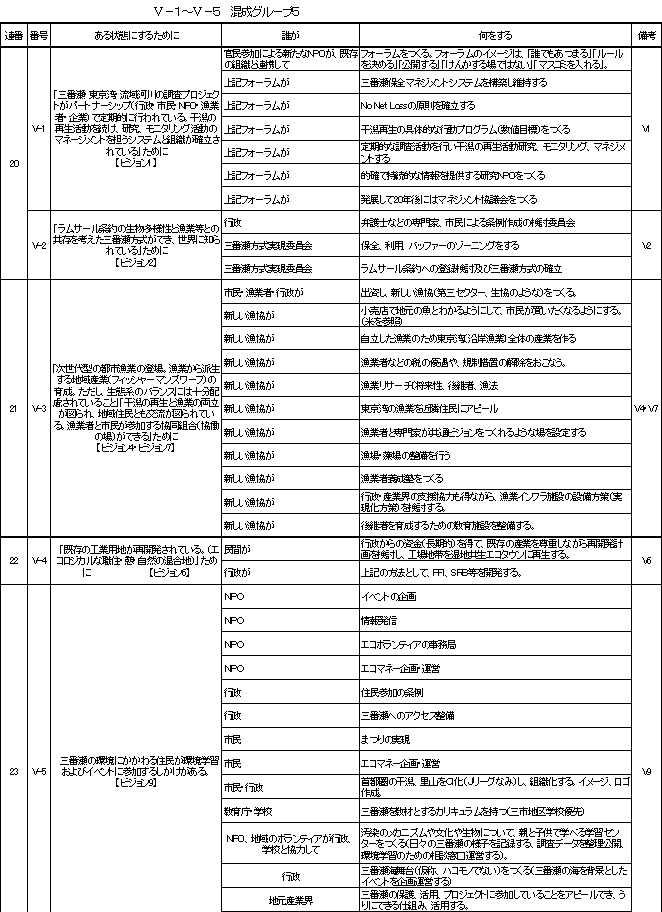
�T�@���[�̂��߂̍s���v��ƌ���
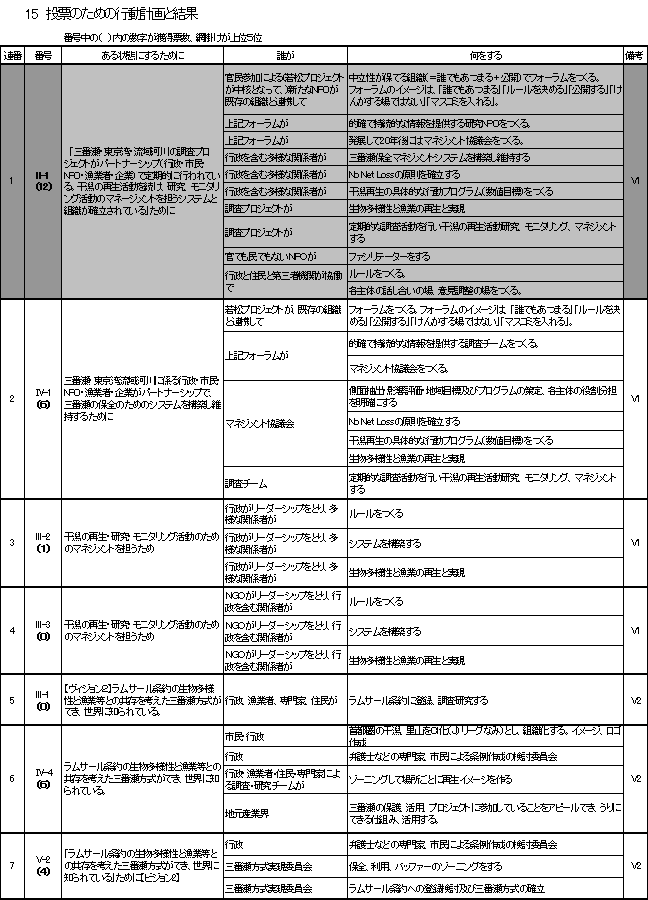
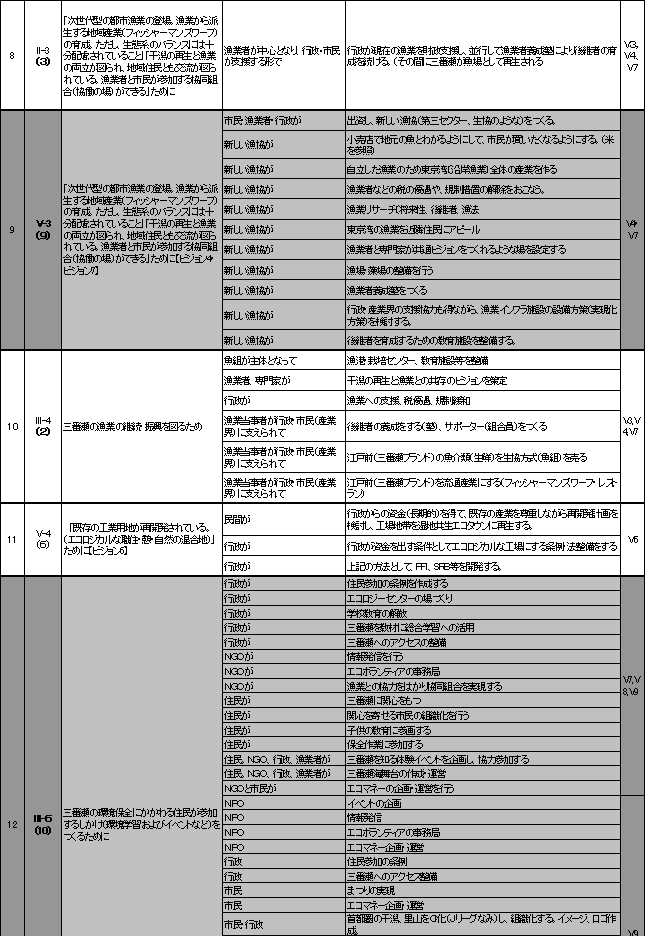
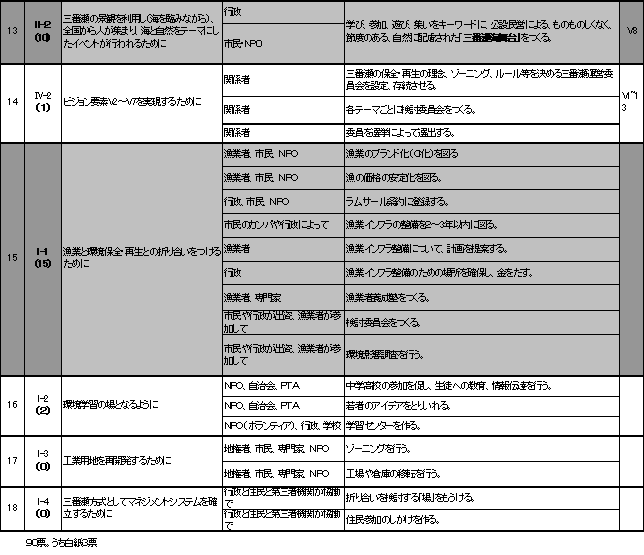
|