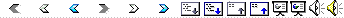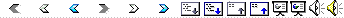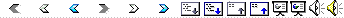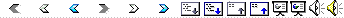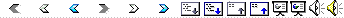|
1
|
- 2003年5月17、18、31日
- 午前10時〜午後5時
- 千葉工業大学津田沼校舎7号館
- 主催:「開かれた科学技術政策形成支援システムの開発」研究プロジェクトチーム
- 後援:三番瀬再生計画検討会議・千葉県
|
|
2
|
- 主催者挨拶
- いくつかお知らせとお願い
- 開催の目的など
- シナリオ・ワークショップとは
- このワークショップに関わる人々
- このワークショップの進め方・ルール
- 四つのシナリオについて
- 最初のグループ討論に向けて
- ファシリテーター(グループ・リーダー)紹介
|
|
3
|
- 非公開とメディアの取材
- マニュアル、シナリオ、「関わる人々」リストなど
- 飲み物=ご自由にどうぞ;会場内禁煙
- 昼食=会場で取っていただきます
- 交通費についてのお願い=31日に一括してお支払いします
- 名札=「関わる人々」リストを参照してください
- 呼びかけは「さん」づけで
|
|
4
|
- 日本科学技術振興事業団・社会技術研究公募型プログラムの中で、
- 2002年1月から2004年12月まで
- 「開かれた科学技術政策形成支援システムの開発」研究プロジェクトが活動する
- このプロジェクトの中で、社会実験として、
- シナリオ・ワークショップという手法を試行するもの
|
|
5
|
- 参加型手法の
- 現実的課題を対象とした試行によって
- 研究プロジェクトの目標とするシステム設計の参考とする
- 三番瀬再生計画作りへの寄与を期待する(単なる社会実験で終わらないことを切に希望する)
|
|
6
|
- 主催するのは本研究プロジェクト
- 円卓会議、千葉県が後援するが、事業の責任は本プロジェクトにある
- この試行は、円卓会議、千葉県庁、そして課題に関わる多様な人々の同意・協力によって可能となった
- 試行の結果をどう用いるか(用いないか)は円卓会議・千葉県の判断による
|
|
7
|
- このワークショップは非公開
- メディアへは、17日、31日の最初の全体会を公開する
- 18日、31日にはスケジュール終了後、メディアに成果を公表する(これらは出来る限り早く、当プロジェクトのホームページでも公開する)
|
|
8
|
- 「持続可能な都市」(都市のエコロジー)計画を
- 参加型で作るために
- 1992年にデンマークで生まれた
- 今EUの諸都市で用いられている
|
|
9
|
- ワークショップと呼ばれる方法の一つ
- 特徴
- 課題についての未来像を作るために複数の「シナリオ」を予め作って、用いる
- 参加者の間で共有できる未来像を作る
- その未来に向かうための行動計画を作る
|
|
10
|
|
|
11
|
|
|
12
|
- ワークショップ参加者
- ファシリテーター(グループ・リーダー)
- 運営委員会
- 事務局
- 事務局ボランティア
- # リスト参照
|
|
13
|
- このワークショップの主役
- 公募市民(11名)
- 個別依頼(4つのセクターから)
- 専門家(6名)
- NPO(意見団体)(6名)
- 議員(3名)
- 産業界(5名)
- 当初の計画の6グループから5グループになった
|
|
14
|
- ファシリテーター:参加者の皆さんが討論しやすいように会議を運営する
- グループ・リーダー:ここでは、グループ討論のファシリテーターという意味で、それぞれのグループの「リーダー」ではない
- ファシリテーターは討論の内容には関わらない
|
|
15
|
- このワークショップが公平・公正に運営されることを保障する組織
- プロジェクト外から3名、プロジェクトから3名で構成される
- 公募市民の選定を行った
- 運営委員が討論に関わることはない
|
|
16
|
- 本研究プロジェクトメンバーが事務局を構成する
- 事務局ボランティアは運営に協力する
- 事務局・事務局ボランティアはこのワークショップの議論には一切関わらない
- 事務局・事務局ボランティアはこの試行(社会実験)の記録を取る
|
|
17
|
- マニュアルのスケジュール=進め方とルール(EUのやり方とは設計が少し異なる)
- このワークショップの全体司会・進行は主催者(研究代表者:若松)が行う
- 全体会のファシリテーターは嵯峨創平氏が務める(ただし、6回目、9回目は若松が共同ファシリテーターとして加わる)
|
|
18
|
- ここでの「シナリオ」=20年後、2023年の三番瀬とそれを取り巻く人と町の「姿」を描いたもの(映画や芝居のシナリオとは異なる)
- 何を優先して考えるか(生物多様性・人間の快適性や利便性)によって、主催事務局が4つ描き分けた
- シナリオは共有できる未来像を作るための手がかり。4つのうちのどれかを選ぶものではない
|
|
19
|
- まず「氷を割り」!(スケジュールの微調整も)グループ討論に入る
- 17日、18日の討論での原則:実現可能性、実現に至る方法の制約などを考慮してよいが、それを理由に未来像を強く制限しない
- 課題は大きく広がっている。関わる機関(行政機関だけでなく)・人々も多様である。その範囲は国、県、市など、限定せず、参加者の皆さんで考えていただきたい
|
|
20
|
- ファシリテーターのやり方はそれぞれ異なるところがある
- グループ・リーダー(担当グループ)紹介
- 全体会ファシリテーター紹介
|
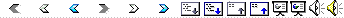
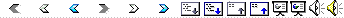
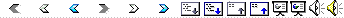
 ノート
ノート